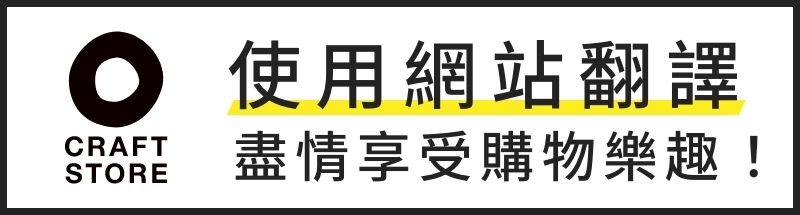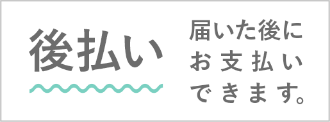ASAKURA
KIRI Coffee Canister









コーヒー豆と、嫁入り道具

昔から晴れ着を保管するなら、桐たんす。
時代こそ感じるけど縫製の素晴らしいドレスや、母娘が着た振袖なんかはそれにしまわれてたりする。
思い出がぎゅうっと圧縮されたような引き出し。
何十年も前のいっちょうらが色褪せないのは、なかなか凄いことだ。

意外なことに、これがコーヒー豆にも一番いい。
高温多湿な夏、乾燥する冬。日本の気候は、衣服にもコーヒー豆にも過ごしづらい。
そんな環境から宝物を守ってきたのが「桐」なのだ。
コーヒー豆もデリケート

それも、生鮮食品と言われるくらい。
すぐに飲みきる場合は常温でも大丈夫だけど、3週間〜1ヶ月の期間であれば、冷蔵庫に入れないと味が落ちてしまう。
コーヒー豆が劣化してしまうのには、空気・湿度・光・温度の4つが大きく関わっています。
そこで重要となるのは、やっぱり保存方法。クラフトバックやアルミの袋でも保存はきくけどそれでは不十分。
一番いいのは密封性が高く、遮光性のあるキャニスターなんです。
生きている素材

コーヒー豆の天敵は、水分。
湿度が上がればその分どんどん味が落ちる。温暖湿潤な日本では、季節によって湿度が
コロコロ変わります。
それに対応できるのはガラスでも陶器でもなく、桐だけです。
桐は外気に合わせて膨張・収縮するので
内部の湿気を一定に保てるのが特徴。
そのおかげでコーヒーが傷みにくく、風味や香りを長く閉じ込められる。
だから、日本で使うなら桐がいい。
音にこだわった密封性

きゅぽんっ。という音が品質の証拠。
木と木が隙間なくぴったりと組み合わさっているか、蓋を開けた時の音で職人が確かめます。
形は、昔は薬入れとしても用いられていた「印籠構造」を採用。
二重構造になっていて、高い気密性で酸化を防ぎます。
酸化を防ぐ、素材のチカラ

桐は弱アルカリ性の木材。
一方でコーヒー豆は弱酸性。両者の間で中和が起こり、酸化が進まない。
つまるところ、劣化を防いでくれるんです。
また、桐は多孔質な木材でもあります。発泡スチロールと同じ原理で、空気の層は水分や温度の変化を伝えづらい。
これまた、美味しさを長持ちさせてくれます。
長く付き合うコーヒーグッズ
お手入れは水洗いは避けて、乾拭きか、強く絞った布で拭いてあげましょう。
汚れやすい上口にはステンレスが施されているため、こちらも拭きとって完了。
挽いた後の豆は表面積が広がり、酸化のスピードも3〜5倍になってしまうので、挽く前の豆の状態で保存するのが一番。
美味しさも逃げないし、汚れも出にくいです。桐は、湿気で歪むなどの狂いが少ない材質。
たんすと同様に、長い付き合いができます。
和を慈しむ心を革新的に
昭和25年、朝倉泰一さんが新潟県加茂市にて「朝倉タンス店」として桐たんすの製造をスタートさせました。
それから68年間、桐一筋でものづくりを続け、コンクールでの受賞や、国際的な家具見本市への参加など伝統を守りつつ、アグレッシブさを見せる家具屋さんです。
二つの木の表情

カラーはすべすべになるまで削り込んだ「木地仕上げ」(右)と、燃える寸前で消火する”焙り色付け”を行った「焙煎仕上げ」(左)の二種類です。
焙煎仕上げは手垢がつきにくく、抗菌効果があります。
サイズは100gと200g

コーヒー豆の常温保存はだいたい2週間ほど。
その期間で飲みきる量を目安に選んでみては。
ちなみに、100g=10杯分くらいです。
日本のコーヒーブレイクに

桐箱に宝物をつめる文化。
日本の気候にあったものづくりが、今も受け継がれています。
- 詳細情報
-
材質:新潟県産桐/ステンレス
生産地:新潟県新潟市※モニターの発色具合によっては、実際のものと色が異なる場合があります。
- 使用上の注意
表面のお手入れは乾拭き、または水を含ませ固く絞った布で拭いてください。
内部のお手入れは、乾拭きで拭いてください。
水分が入るとカビの原因となります。本体と蓋の仕込み作業は、職人が1個ずつ微調節をしながらお作りしているので正しい組み方(木目が合うように)でご使用ください。
蓋が緩くなったりきつくなったりしますが、桐は湿度に反応して伸縮し内容物を守るため、ご使用には問題ありません。
- ブランドについて
-

ASAKURA
朝倉家具は1950年創業の桐たんす製造元です。伝統の技を大切にしながらも現代の生活様式に対応した、創造性あふれるモノづくりに取り組んでいます。職人たちの手から生まれる丁寧な仕事と、”桐”のやさしい素材感。
- アイテム評価
-
この商品に寄せられたお客様の声はまだありません。
レビューをするためにはログインが必要です。


こちらもおすすめです
いま人気のアイテム
最近見たアイテム
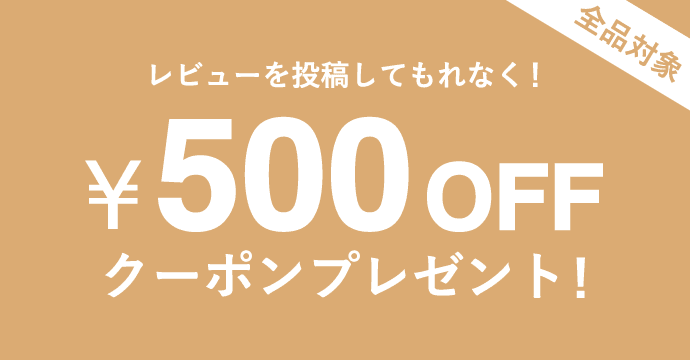


- 送料/発送
-
CRAFT STOREよりお届けします。
送料(全国共通)880円
※合計11,000円以上の購入で送料無料。
製造元の在庫状況によりそれ以上お時間を頂きそうな場合は、別途ご連絡させていただきます。 - お届けについて
- 配送 配送方法は以下の通りございます。 CRAFT STOREよりお届けいたします。 発送日の目安について 期間を要する商品については、商品ページにて発送日の目安を記載しております。 生産状況・欠品等の理由で発送日の目安を超えてしまう場合、CRAFT STOREよりご連絡いたします。 長期休暇の配送について 長期休暇(年末年始、GW、お盆)の配送およびご注文の対応につきましては随時お知らせを出しておりますのでそちらをご覧ください。 包装 化粧箱、破損防止の包装をして発送いたします。
- お支払いの方法
-
「クレジットカード決済」、「コンビニ支払い」、「後払い(コンビニ・郵便振替・銀行振込)」、「Amazon Pay」、「代金引換」の6種類からお選びいただけます。
クレジットカード決済

後払い
決済手数料:330円(税込)
お支払いの方法の詳細についてはショッピングガイドをご参照ください。電子マネー決済

代金引換
決済手数料:330円(税込)